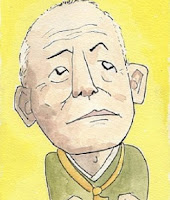山爺は悠々でも気ままでもないがいわゆる年金暮らしである。ゆえに慢性の金欠病により軍資金は乏しいが暇だけはたんとある。
それにしても連日寒い日が続くので気が滅入るし散歩も億劫だ。以前なら寒くても体が疼くのでノコノコと外出したものだが最近はさっぱり、こたつにデ~ンと入ったきりでWOWOWの洋画ばかり見ている。加齢病の副作用ということか。『いかん~いかん、これでは、いかん』・・笠智衆の声色で・・ (^^♪TVの天気予報を見ていると3月1日(土)は気温も上がり陽気が良いとのこと。また梅も各所で咲き出していると報道している。梅の撮影にでも行こうか。
重い腰を上げたのには他に理由がある。
ヤフオクでまたもやNikon1眼レフ、D3100という機種を¥4500(送料込)の格安で手に入れた。このカメラの特徴は従来のDシリーズより一回り小さく、より軽量設計なので里山歩きや旅行用に重宝することだ。かねてから欲しい機種のひとつであったが、新品はボディのみでも6万5千円以上、年金爺にはとても手が出ない。
いったいにカメラが高額なのはその驚くべき部品点数によることだ。以前半蔵門にあるカメラ博物館を訪ねて展示してあった一眼レフカメラの構造と分解部品を見て魂消た。たしか1000点以上の部品で成り立っているようだ。改めて高級カメラというものが相当の部品製作費用と組立工数で成り立っていることを認識した。
なるほどなあ、高額なのも納得だ。『これに比べたら家電品の製作なんぞはへのカッパだなあ』・・・・もと家電メーカー勤務者の独り言。
またこれだけ細かい精密部品の集合体である。これをなし得る技術を持った国は当然限られるなあと感心したもんです。隣国のC国やK国はまだ無理だろうなあ。
山爺が落札したヤフオク出品の状態は”動作確認済み”との説明であったが、そこはオークション、実際に手に取って確認するまでは不安だ。
なにせヤフオクに掲載している品物は”動作保証せず”などはまだ良い方で、シャッター降りません・電源スイッチはいりません・電池蓋欠損・はてはレンズ割れてます、などのガラクタが堂々と出品されている。そんなもの誰が買うかって?・・・それが買うんですよ。部品取りして自分のカメラの修理に使うんです。メーカーから純正修理部品購入すると目ん玉飛び出るほど高額だからねえ。また本体は不要で付属しているストラップ・充電器・レンズが目当ての人もいます。
猛者になるとガラクタばかり数台落札して寄せあつめ、再組立して1台の動作品に仕上げ再びオークションに出品するか、中古ショップに持ち込んで利ざや稼ぐ。この世界は奥が深いのです。
D3000シリーズが出品されるたびに動作品で値頃な物を選んで入札していたがオークション締切(20時~22時が多い)間際の数分間に¥100程度ちょい上乗せされてオークションに手馴れた者にさらわれる。山爺はそこまでのセリ根性は持ち合わせていないのでなかなか落とせない。そんな事の繰り返しだったがついに安価ながら状態の良さそうな物を落札した。宅配便の包装を開けるのも、もどかしく・・出てきた商品の外観をチェック。『おお、綺麗ではないか』新品同様で傷が見当たらない・・第一関門クリアーだ。
レンズを装着し電源を入れ適当な被写体にカメラを向けてピント合わせ。オートフォーカスもピシャリと動くし試し撮りも大丈夫だ。『よし、こりゃあ良さそうだわい』・・と、心うちでガッツポース。落札商品の”無事確認”、この瞬間がたまらないんだよなあ。
これで山爺の所持するニコン一眼レフカメラはベースのD50、モニターが可変するD5000、小ぶりのD3100と3機種そろい踏みとなった。ちなみに若い頃大枚をはたいて購入した光学フィルム式のニコン一眼レフカメラも大事に持ってますよ。
ご存知のとおりニコンは世界に名立たる名器で報道カメラマンほかプロのほとんどがこのカメラを使っている。現在国内生産はしていなくタイ国・中国に全てシフトし終えたことにより若干安価になったとは言え小型カメラに至るまで今持って高額商品だ。
一昔前ならニコン一眼レフを3台も揃えるのはよほどの趣味人かプロのカメラマンでないと叶わなかったが時代が変わったんだねえ。皆んな裕福になり手に入れたものを簡単に手放して次々新製品に買い換える。山爺の嫌いな言葉『断捨離』がここにもある。・・・ってか。
3機種の違いをまとめたのが下表であるがD50と比較するとD3100は115gも軽い、この差は大きいねえ。
 D50とD5000・D3100、構造上大きく違うのがD50は自動ピント合わせの駆動モーターがボデイに内蔵されているのに対してD5000・D3100は原価低減・小型化を目的?とし交換レンズ側に駆動モータを組み入れたことだ。それらのレンズは駆動モーターのないものをAF、駆動モータ内蔵のものをAF-Sとして区別している。
D50とD5000・D3100、構造上大きく違うのがD50は自動ピント合わせの駆動モーターがボデイに内蔵されているのに対してD5000・D3100は原価低減・小型化を目的?とし交換レンズ側に駆動モータを組み入れたことだ。それらのレンズは駆動モーターのないものをAF、駆動モータ内蔵のものをAF-Sとして区別している。
D50シリーズはAF・AF-Sともに自動でピント合わせが可能だがD5000・D3100にAFレンズを装着すると駆動モータが存在しなくなるのでピント合わせは手動(M)モードのみとなる。
まあ、専門的なことはこれぐらいにして。新しいカメラが手に入ったので試し撮りがしたくてウズウズ。そんなときにTVニュースで気温が3月下旬並みで陽気も良く梅が各所で満開とのこと、これは行かねばなるまい。
さて、どこに行こうか。
去年10月に訪れた向島百花園はもともと梅の名所だ。入場料も65歳以上は70円とタダ同然。そこに行ってみよう。百花園を見終えたら駅に戻らず隅田川に出て桜橋を越え右岸へ渡り猫神社で有名な今戸神社をお参りして浅草に抜けてみよう。
ちなみに右岸とは川の上流を背にして右手を指します。勉強になりましたねえ。
『馬鹿にするな、それくらい知ってるわ』ですって。・・登山の専門家でも右岸と左岸の定義を間違えて道に迷い、遭難死した事例があるので念のため申し上げました。
・・ (・∀・)
午前10時に百花園到着。マイナンバーカードを提示して70円を支払い入場する。
入園すると、いきなり赤や白の梅が目の前に飛び込んでくる。
 おお、いいねえ。文字通り、ちょうど良い”塩梅”ではないか。急ぎカメラを構えてぱちり。背景に偶然スカイツリーが入った。都内には著名な被写体が、ここ、かしこにあるのでカメラの趣味人にはたまらない地域のひとつなんだなあ。
おお、いいねえ。文字通り、ちょうど良い”塩梅”ではないか。急ぎカメラを構えてぱちり。背景に偶然スカイツリーが入った。都内には著名な被写体が、ここ、かしこにあるのでカメラの趣味人にはたまらない地域のひとつなんだなあ。
園内には自慢のカメラをブラ上げた中年男のカメラ小僧ならぬカメラ爺いがちらほら見受けられます。・・・って、わしもそのひとりかい。傍らには春の七草があしらってありました。憎い演出ですなあ。
ちなみに春の七草とはせり、なずな、ごぎょう、はこべ、ほとけのざ、すずな、すずしろを言いますが、山爺はいつになっても覚えきれません。
まずはスカツリーと白梅のコラボ。紅梅は艶やかですなあ。
白梅も満開です。
でも、梅と言ったら白梅(しらうめ)に軍配が挙がるのですかねえ。山爺は白梅の方が好きです。
紅梅もそれなりに綺麗ではあるが何かケバくて厚化粧の軽い女を連想してしまう。水仙もまだ負けずに頑張ってます。

あたしも見て、見て、と福寿草。
動物も負けずにポーズ・・
あれぇ、ファインダー越しに覗いてよく見ると陽気に誘われ昼寝してる?みたいだ。
のどかだねえ。
こちらは番(つがい)かな?仲良さそうです。
鳥の番のおおくは一旦連れ添うと死ぬまで一緒と聞きますが素晴らしい習性ですねえ。
それに比べて人間と言ったらあなた・・何十人と取っ替え引っ替え、ひどいもんですなあ。
入口にサイフォンが飾ってありましたが、今時珍しくサイフォンで入れてくれるのかなあ。・・・まだ散策の半ばなので我慢、我慢。
隅田川に出ると土手に一本の河津桜が・・・満開で綺麗に咲いてました。
隅田川の下流に向かってのんびり歩く。山爺は野山の景色を眺めながらの里山散策が好みだけれどぶらり散歩していると期せずして名物被写体に出くわす都内の散歩も好きである。
また都内はいたるところに路線バスが走っているので疲れたらぽんと飛び乗れば必ずどこかの駅に連れて行ってくれる。どこまで乗っても定額なのが何よりだ。
隅田川の正面にア〇ヒビールの本社社屋が見えてきました。有名な黄金ウ〇コオブジェの先っぽだけが見えてます。
食品を扱う会社にとって最大不名誉なあだ名がついてしまっているオブジェだが山爺も設置当初にこれを見た瞬間にウ〇コだ、と直感した。
果たしてこのオブジェの正体とは何なんだ?
【山爺の一言メモ】
ア〇ヒビールの広報を検索してみると、質問に対し(そりゃあ毎日かなりの質問が来るだろうなあ)以下の回答が記されていた。
・聖火台の炎をイメージ
・金色の炎は「新世紀に向かって飛躍するア○ヒビールの燃える心」を表している。
・設計者は有名なデザイナーであるフランス人のフィリップス・スタルク氏。
・ア〇ヒビール100周年の記念事業の一環として1989年に竣工
とありました。
うーん、どう見ても聖火台の炎には見えないなあ。どこから、どう見ても黄金色のウ〇コだよ。
山爺はこう考える。・・・これはあくまで山爺の私見で洒落ですから苦情やお叱り等のご意見は無用に願います。 m(_ _)m
フランスの著名なデザイナーフィリップス某にオブジェの制作を依頼した1980年頃の日本はバブルの絶頂期だ。もともと欧米人の多くは有色人種を蔑視する傾向にある。
フランス人であるフィリップス某もバブルで大儲けをしている有色人種たる日本のことを愉快に思うはずがない。
アジアの猿共にはこんなもので十分だ。と、ふざけ半分に創作したのが件のオブジェに違いない。聖火の炎なら縄文土器のようにばらけて赤色に作るのが普通だろう。
提案されたア〇ヒビール側は西洋人の著名なデザイナーに対し反論することができない。外国人コンプレックスも相まってとうとう竣工に踏み切らざるを得なかった。日本人が設計したらこうはならなかったろうねえ。日本人同士なら遠慮なくクレームをつけるのが常だから。・・・ (^^♪
しかもこのオブジェは10数年に一度大々的に塗り直しをしているとか。・・ウ〇コオブジェと言えども維持管理し綺麗にしなければならないとは、大変だなあ。・・ウ○コは汚れたままで良いのでは?ア〇ヒさんには悪いが何か笑える。
まあ、今持って質問が相次いでいるほど有名になり浅草の名物になってしまったのだから広報的にはある意味大成功だったのではと思う。以て瞑すべし、なんちゃって。
ちなみに隣の金色の四角いビルはビールのジョッキーを模しているとか・・皆さん知ってましたぁ。山爺はちいとも存じ上げませんでした。こちらは日本の会社が設計したので十分議論した?からまともな形に出来上がっている。で、逆に全然有名にならないとは皮肉なもんだねえ。
そうこうとゲスの想像をしているうちに今戸神社に到着しました。大鳥居の脇に沖田総司終焉の地との看板が掲げてある。
はて?司馬遼太郎の新選組血風録によれば沖田総司は千駄ヶ谷の植木屋宅で亡くなったとあったはずだが・・・
調べてみるとこう言いうことらしい。
京都より戻った総司は新選組の産業医(作者注:当時そんな職業あるか馬鹿者)だった松本良順の家が今戸神社近くにあり当初そこで療養していた。のちに千駄ヶ谷の植木職人平五郎宅に療養先を変えたという記録が残っている。
今戸終焉説は同じ新選組隊士で大正の世まで生き延びた永倉新八(1915年75歳で没)の証言が元になっているようだが永倉は沖田が今戸神社で療養中に江戸を離れて東北へ転戦している。
ゆえにその後、沖田が今戸から移動したことを知らないはずで誤った情報を仲間に伝えたのだろう。昨今の新選組ブームで婦女子には土方歳三と双璧の人気者だ。終焉の地として神社が利用するのも頷ける。
当時は官軍の連中が新選組の残党を血まなこで探している時だ。総司も例外ではなく、否、かつて薩長始め勤皇の志士の多くを倒した総司こそ相当憎まれたいたはずだ。ゆえに松本良順の傍に置いていたのでは危ういと考えて往診しにくくなるが良順の住居から離れた千駄ヶ谷に避難させたのかも知れない。
今戸神社の創建は1063年、主祭神は応神天皇・伊邪那美命・伊邪那岐命。
当初は京都の石清水八幡宮として勧進したが1937年近隣にあった白山神社を合祀し今戸八幡から今戸神社と呼ばれるようになったそうです。
そんな今戸神社も今は縁結びの神社として、近々では猫神社として若者たちの人気神社だ。
今戸神社が猫神社になった理由は江戸時代にさかのぼります。
【山爺の一言メモ】
江戸時代、あるお婆さんが猫を飼っていたが貧乏で買い続けることができず泣く泣く手放した。するとその猫が夢枕に立ち、我が姿を人形にして商いせば福徳がとのお告げ。早速今戸焼の猫人形を作って売ったところ大評判でお婆さんは幸せに暮らしたとか。
この招き猫の姿をした今戸焼はその後、今戸神社の名物として人気商品となり今日に至っています。職人による手作りなので一体ずつ顔立ちが違うので今も大人気だとか。
でも、この神社が猫神社として近年大賑わいになっているのは他にも理由がありました。
いつの頃からか神社境内に白猫がぶらりと現れるようになったんだとか。名前はナミちゃん(今戸神社の祭神イザナミから取ったようです)
いつも神社にいるわけではないのでいつしかこの猫を目撃した人には幸運が訪れるとの噂が流れます。
やれ彼氏が出来たとか、良縁に恵まれたとか、商売が繁盛、果ては宝くじ高額当選まで。やがてこの噂を聞いた人がわんさか押しかけるようになって神社自身も御朱印ほか縁起物が飛ぶように売れて大繁盛?。ナミちゃん様々、まさに招き猫そのものだったとか。
残念ながら今年一月に亡くなったようですが年齢不明ながら相当長寿だったようで人間で言うと100歳近くの大往生だったとか。
神社の本殿をよく覗いてみると確かに白猫の遺影が祀られてます。ナミちゃん神様になっちゃったんですねえ。大した猫ちゃんです。
昨今の海外からの観光ブームで外国の方々がこの神社にも数多く訪問しているようで、境内に奉納された絵馬に英語の書き込みがありました。 すっかり楽しい雰囲気でいたのですが不愉快なことも耳にしました。
山爺が縁起物の猫マスコット付きのおみくじを購入したとき、社務所の人と交わした会話。
『大繁盛ですね』『おかげさまで』・・ここまではよかったが、社務所の人から『でもC国の人は境内に飾ってある招き猫を断りなく持って行ってしまうので困っています』『え、そりゃあひどいなあ』
それも1人や2人ではないようです。何だかなあ、縁起物として失敬するのか、警備薄だから儲け、儲けと思い盗むのか・・山爺としては前者の理由だと思いたいが、相変わらず民度が低いねえこの国の人々は。このようなことを平然としているうちはC国、恐るるに足らんと山爺は考えている。
さて、このあとは浅草界隈の散策に出かけよう。
【川柳】
・言問に 聖火に見えぬ 大オブジェ
・炎には 見えぬ隅田の 黄オブジェ
・今戸では ニイハオと言う 猫さらい
・今戸には 猫も招かぬ 人も来る
***************************************
①ここに掲載されたルポや川柳の著作権は作者(日暮道長)にあります。
②作者以外の方による無断転載は禁止で、行った場合、著作権法の違反となります。
読後の感想をコメントまたはメールしていただけると幸いです。








.JPG)